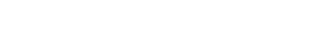時宗 紫雲山 宝林院 新善光寺縁起

時宗
紫雲山宝林院 新善光寺
栃木県小山市卒島七八四
本尊 弥陀三尊(善光寺如来)
全国善光寺会会員
弘安三年(1280年)宗祖一遍上人開創
元応元年(1319年)二祖真教上人開基
伝に曰く、『栗崎道場紫雲山宝林院新善光寺と称し、小山町上宿に七堂伽藍(塔・金堂・講堂・鐘楼・経蔵・僧房・食堂など七つの建物が完備しているもの。)の大寺があり、ご本尊は閻浮檀金(閻浮樹の森を流れる川の底から取れるという赤黄色の良質の金のこと。)信濃の善光寺如来一体分身の御仏なり。元禄年中、乱世の当時に仏像は盗賊の被害に遭い、その後は兵火によりついに廃滅となると云う。』
当山が現在地に建立されたのは、今から約300年位前と推定され、それ以前は卒島字道場(現在地から西方約1km)にあったと伝えられています。
なお、開山当時の所在地である小山町上宿から卒島道場に移ってきた経緯など、はっきりとしたことはわかりません。
現在の本堂は、昭和47年に従来の古いかやぶき屋根を解体して新築し、さらに平成13年に一部を改修して今日に至っています。
(古い本堂解体時の宝永7年、建築270年と推定されます。)
当山は、多賀谷城主子孫が守って来た寺で、朱印70石と伝えられています。
戦前 檀家数 約80戸
寺有地は境内地及び墓地を含めて2700㎡、他に田畑約2ha(現在 田畑なし)
(参考)
永仁5年(1297年)6月 二祖真教上人が当山如来堂にしばらく逗留されました。
その時「端花(豊年の兆しとなるめでたい花のこと。)降り、紫雲たなびく端相(おめでたいこと。)がしきりと起こり、人々の耳目を驚かせた」と伝えられています。
「一遍上人縁起絵」第六巻第四段 遊行寺蔵


新善光寺三十三観世音菩薩略縁起


遊行四十七代唯称上人(時宗四十七代目のお上人さま。)は、若い頃より観音さまを深く信仰され、有縁(仏さまや観音さまなどに会い、教えを聞く縁があること。)の地に観音堂を建立し、その大恩に報いたいと考えておられました。
元禄十六年(1703年)春、唯称上人が御親教(宗祖一遍上人以来、代々のお上人さまが全国を布教して廻る旅のこと。)で当山にご逗留(旅先などで一定期間とどまること。)されました。
不思議なことにその夜、観音さまが三十三身に変現して大光明を放ち、「当地は、我が有縁の地であるが故に永くこの地にとどまり、来世の衆生に結縁(仏さまや菩薩さまが世の人を救うために手をさしのべて縁を結ぶこと。世の人が仏法と縁を結ぶこと。仏法に触れることによって未来の成仏・得道の可能性を得ること。)すべし」と唯称上人にのべられました。
唯称上人は、このお告げに深く感激され、当時の住職に依頼して観音まさ三十三体を安置して開光供養会(安置した観音さまに魂を入れること。)を行い、もろもろの人々に結縁したことが、当山三十三観音菩薩像の霊光発輝のはじめと伝えられています。
安置する観音さまは、相好円満一つも欠けることなく、慈眼視衆生・福寿海無量(観音さまは一切の功徳を持っておられ、慈悲の眼をもって命あるすべてのものをご覧になっておられます。そして、すべての迷い苦しんでいるものを救って、悟りの境地に導こうとしておられます。観音さまとは大海のように無量無限の福徳を持って命あるすべてのもののために垂れ給うご存在であるからです。だからこそ我々は観音さまを信じて礼拝し「南無観世音菩薩」とそのお名前を唱え信仰に励むべきという意味のこと。)というお経に説かれています。よって、遠近より日々多くの老若男女がお参りに訪れました。
特に当山は今から七百有余年前、遊行の宗祖一遍上人が当山に逗留されたとき、不思議なことに突然蓮の花が空中に舞い、お参りに来ていた人々を驚かせました。
そしてこの不思議な出来事からさらに多くの参詣者が訪れたと、国宝「一遍上人絵詞伝」に描かれています。
故に観音さまを信じお任せすれば、尽きることなき慈悲の願海を浴びることができることでしょう。
小山慈照観世音菩薩像
当山に安置する小山慈照観世音菩薩像、昭和中末期における国道4号線(俗に「死号線」と呼ばれていた。)が通過する栃木県小山市における交通死亡事故の多発を深く憂い、当代49世 成阿 健雄(健志)上人の発願により、市民の交通安全の願いを成就すべく建立されたものである。


善光寺について
善光寺ご本尊の一光三尊阿弥陀如来は、欽明天皇13年(552年)仏教伝来の折百済の国から我が国に渡れた日本最古の仏さまで、皇極元年(642年)本田善光卿によって、都を遠く離れた遠地へと下向された。
その後、仏さまは秘仏となられ、直接そのお姿を拝することができないが、法灯連綿として1300有余年の時を経て、今なおすべての人に現世の安穏と極楽往生を約束してくださる大慈悲の仏さまとして、全国から厚い信仰を得ている。
永代供養のご案内
「あなたの後々の憂いが少しでも楽になりますように・・・」
- 将来、ご先祖さまのお墓を守る者がいない。
- 子どもが嫁ぎ、我が家のお墓を守る負担をかけたくない。
- 独り身のため、お墓は得たいが供養してくれる者がいない。
- お墓を維持していく費用や管理が困る。
お墓のことでお困りの方、あなたに代わり、永代ご先祖様のご供養及び管理を当山が承ります。 合掌
【納骨方法】
一定期間、本堂内に安置し、その後は永代供養墓に合祀します。
合祀とは、骨壺からご遺骨を取り出し、他の遺骨とまとめて埋葬することを言います。合葬とも呼ばれます。
【永代供養のご志納】
一霊20万円 複数納骨をご検討の場合はご相談ください。
※名板をご希望される場合は、別途費用(一霊 15,000円程度)がかかります。
名板とは、永代供養墓西側にあり、永代供養墓に埋葬されている方の戒名(法名)・生前の名前・没年月日・亡くなった時の年齢などを記す石板です。
なお、名板の有無に関わらず納骨の記録は、寺に保管する過去帳に記録は残ります。
※以後の維持管理費用は一切かかりません。
【その他】
供養のご志納に含まれるものは、納骨時のご供養及び当山で毎年行われる、お彼岸、お盆、お施餓鬼、元旦のご供養等です。
※通夜・葬儀、戒名授与、年回のご供養は含まれません。
(ご希望の方はご相談ください。)
【ご利用のお約束とお申込み方法、その他】
- それまでの宗旨・宗派は問いません。(当山のお檀家以外でも構いません。)
- すでに納骨されている方の改葬(墓じまい)もお受けいたします。
但し、これまでの菩提寺へ当山に納骨の許可を必ず得てください。 - 納骨の際や常例のご供養の仕方は時宗の法式となります。
(時宗の法式は「南無阿弥陀仏」のお念仏を称えます) - 生前申込者の葬儀は必ず当山で行ってください。
- 別に定める「永代供養規定」に承諾の上、申込用紙にてお申込みいただき、ご供養のご志納をお納めいただいてから利用許可となります。
- 納骨後のご志納の返還及び、合祀後の返骨は一切できません。
- 当山護持会へのご加入もお受けいたします。
納骨堂


永代供養墓「悠久之碑」

令和4年5月建立
永代供養お申し込み後、本堂内の納骨堂に納め、一定期間が過ぎましたら遺骨を永代供養墓に合祀します。
上記よりPDFをダウンロードして申込書をご記入ください